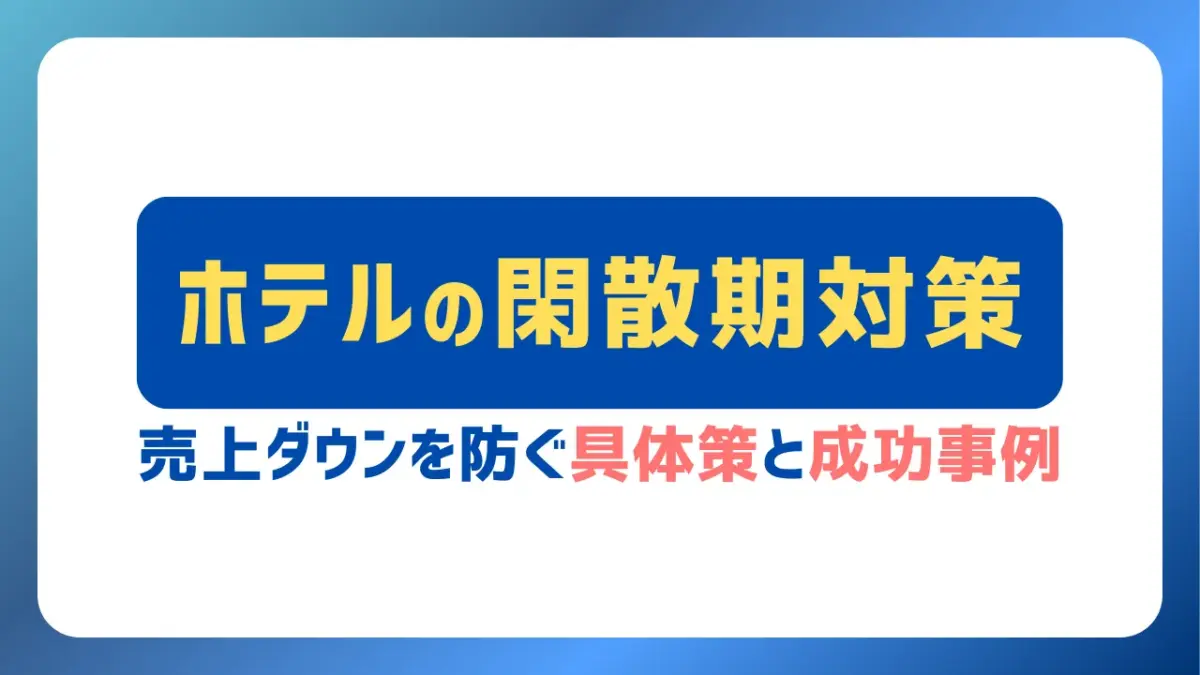
はじめに|閑散期は稼働率40%が当たり前?どう乗り切る?
一般的にホテル業界は、繁忙期と閑散期の差が大きく、稼働率が安定しづらいのが実情です。とくに予約が落ち込みやすい時期には、経営そのものに大きな影響が出ることもあります。
地域や施設のタイプにもよりますが、観光地型ホテルでは、1〜2月や梅雨、秋口といった時期に稼働率が下がりやすい傾向があるというお声をよく耳にします。こうした閑散期をどう乗り切るかが、年間の収益バランスを左右する大きな要素になります。
この記事では、売上を守り、むしろ伸ばしていくためのヒントをデータや事例とともに紹介していきます。
“とりあえず値下げ”に頼るのではなく、戦略的に閑散期を乗り越えたいと考えている方に参考になれば幸いです。
データで見る|ホテルの閑散期とは?時期と影響を正しく把握
まずは、「いつ・どれくらいの影響があるのか」をきちんと把握しておきたいところです。
過去の売上データなどから「1月はヒマだな……」と感じていても、それが地域全体の傾向なのか、それとも自社の販促やプラン設計に原因があるのか、見極めは意外と難しいものです。
こうしたあいまいな感覚を、客観的なデータで可視化することが、最初の一歩になります。
“本当の閑散期”を明確にしておけば、対策の優先順位もはっきりしてきます。
閑散期にできる5つの対策案
対策①|「近距離需要」を狙う地域密着型マーケティング
旅行を控える人が多い閑散期は、遠くからのお客様だけを頼りにしていては空室が埋まりません。そんなときに頼れるのが“地元”や“近隣エリア”の生活者です。
いきなり泊まりたいと思ってもらうのは難しくても、「使ってみたい理由」をつくってあげることで、近場からの新しい需要が見えてきます。
想定ターゲット:
・地元住民(記念日・日帰り温泉・サウナ利用)
・車で90分圏内のファミリー層
・ワーケーションニーズのある個人事業主やフリーランス
施策アイデア:
・「〇〇市民限定プラン」(駐車場無料・割引)
・地元スーパーとのタイアップ企画(レシート提示割引)
・地元紙・フリーペーパーでの告知
対策②|ダイナミックプライシングで“安易な値下げをせずに調整して売る”
値段を下げればある程度の予約は入りますが、それでは利益が削られていくだけ。しかも、一度下げた価格は元に戻すのが難しくなりがちです。
そこで注目したいのが、需要に応じて価格を自動的に調整できる「ダイナミックプライシング」。RMS(レベニューマネジメントシステム)などを活用し、需要の変化に合わせて、価格をリアルタイムまたは短いスパンで最適化する考え方です。
ダイナミックプライシングを活用するためのポイント:
・レベニューマネジメントシステムを活用した価格の自動調整
残室数や予約状況、需要予測に応じて、価格をリアルタイムに自動で変動させ、機会損失や不必要な値下げを防ぐ。
・自施設の需要に基づいた価格設計
競合価格を追いかけるだけでなく、自施設の過去の販売実績や季節性などをもとに、最適な価格を算出する
・ターゲットに応じた柔軟な料金設計
平日割、直前割、長期滞在割などを設定することで、時期や滞在スタイルに応じた価格戦略が可能に。これらはダイナミックプライシングとは厳密には異なりますが、柔軟な価格運用という観点では共通のアプローチです。
対策③|非観光目的の新需要を取り込む
観光需要が減ると「もうお客さんが来ない」と感じがちですが、実際には観光以外の理由で宿泊する人たちもたくさんいます。
例えば、会社の研修や学校の合宿、地域イベントの宿泊など。こうした“観光以外”のニーズを拾いにいくことで、閑散期でも安定した集客が可能になります。
非観光系のターゲット例:
・企業の研修やオフサイトミーティング
・大学のゼミ合宿やスポーツ団体
・行政や地域団体のセミナー・説明会
対策例:
・会議室付き貸切プラン
・団体割+早朝朝食対応
・「貸切で安心」訴求による地域連携
対策④|宿泊単価を下げずに「付加価値」で勝負
値引きではなく、“価格以上の満足”を提供することで、単価を維持したまま選ばれる施設になることができます。
少しの工夫で、「ここにしかない体験」を感じてもらえるような仕掛けをつくりましょう。
付加価値アイデア:
・地酒・地元ワインの試飲付き
・レイトチェックアウト無料
・着物体験・そば打ち・茶道など文化コンテンツ
対策⑤|固定費・人件費を削減し、利益構造を最適化
稼働率が落ちる時期は、売上の増加だけでなく、コスト最適化(利益率の確保)も重要なテーマとなります。
特に人手不足が深刻化する中で、業務の効率化・省力化への取り組みは不可欠です。
付加価値アイデア:
・自動チェックイン端末やスマートロックの導入
・レベニューマネジメントシステムの導入
・よくある質問への対応をチャットボットに一部代替
よくある質問(FAQ)
Q. 値下げしないと集客できないのでは?
A. 限定性や体験価値の高いプランを設計することで、価格を下げずに選ばれる宿泊施設を実現することが可能となります。稼働率を高めるには、価格以外の魅力も磨くことが大切です。
Q. 小規模施設でもRMSは導入できますか?
A. はい。中小施設向けのレベニューマネジメントシステムも存在しており、月数万円〜で導入できるツールが増えています。
Q. 補助金などの支援制度は使えますか?
A. 地域や時期によっては、「観光再生支援事業」「小規模事業者持続化補助金」「中小企業DX補助金」などの制度が利用できる場合があります。観光庁や自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。
成功事例|実際に効果があった閑散期対策の取り組み
成功している施設は、どのようにして閑散期を乗り越えているのでしょうか。
ここでは、実際の事例をもとに、どのような施策が成果につながったのかをご紹介します。
成功事例1:付加価値プランの導入で予約数が1.3〜1.5倍に増加(都内ラグジュアリーホテル)
課題:
施設の魅力を活かした販売訴求ができておらず、シンプルなプランばかりで差別化が難しかった。
施策:
・レイトチェックアウトやアニバーサリープランなど、付加価値のあるプランを新たに造成。
・OTAでのセールや特集に積極的に参画し、露出を増加。
・魅力的な写真コンテンツや表現を用いて、ユーザーに訴求。
成果:
付加価値プランの販売開始により、予約数が通常の1.3〜1.5倍に増加。さらに、施設の強みを活かした販売戦略により、差別化と収益向上を実現。
成功事例2:補助金を活用した館内リニューアルで平日稼働改善(静岡県・熱川プリンスホテル)
課題:
閑散期の稼働率と顧客満足度の向上が必要
施策:
・中小企業庁の「事業再構築補助金」を活用し、館内施設を一部リニューアル
・個室ダイニングを新設
・地域交流の場として、東伊豆ならではの内容を学べるカルチャー教室を設置
成果:
平日利用の増加、地域住民との接点創出に成功
成功事例3:料理プランの明確化とOTA価格調整で客単価を約2.8万円に向上(老舗旅館)
課題:
5種類の料理コースがありながら、名称や価格のみの違いで、利用者にとって選択基準が不明確。結果として、低価格プランの販売が多く、客単価が伸び悩んでいた。
施策:
・プランタイトルに「スタンダード」「ハイグレード」などのキーワードを用い、各プランの特徴を明確化。
・プランの並び順をランク順に整理し、利用者が選びやすい構成に変更。
・OTAでの販売価格を自社サイトより2,000円高く設定し、自社サイト予約を促進。
成果:
利用者が自分に合ったプランを選びやすくなり、転換率が向上。さらに、「松竹梅効果」により、客単価が約2.8万円に伸長し、売上と利益が向上。
まとめ|閑散期は「ピンチ」ではなく「仕組みを変えるチャンス」
閑散期は、単なる売上減少の期間ではありません。むしろ、新しいターゲットに目を向けたり、サービスや運営体制を見直したりすることで、次の繁忙期をより強く迎えるための準備期間になります。
売上を守るための対症療法にとどまらず、将来に向けた体質改善の機会として捉えることが重要です。
例えば以下のような対策を組み合わせることで、季節に左右されにくい収益構造を目指すことができます:
地元・近隣への訴求強化による新たな利用動機の創出
RMS(レベニューマネジメントシステム)を活用した価格戦略の最適化
企業・団体・地域イベントなど、非観光需要の積極的な取り込み
「ここでしか味わえない体験」による差別化とファンづくり
業務効率化や省人化による利益率の改善
施設の立地や客層によって最適解は異なりますが、今できる一歩から着実に取り組むことで、閑散期を「強みをつくる期間」へと変えていくことができます。
